3月の祝日といえば春分の日ですが、そもそも何か考えたことはありますか?私は一度もありません(笑) なので、せっかくなので調べてみました!
春分の日とは、昼と夜がほぼ同じ長さになる日で季節の節目を示す二十四節気の一つです。毎年3月の20~21日に設定され、昔から農作業を本格的に始めるための目安の日にもされてきたとのこと。
春分の日が祝日として制定されたのは1948年の頃。古くから春分の日には「春季皇霊祭」、秋分の日には「秋季皇霊祭」という宮中祭祀が執りおこなわれてきたことに由来します。
春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」、秋分の日は「先祖をうやまい、亡くなった人々をしのぶ日」として国民の祝日に関する法律に記載されています。
春分の日は毎年異なりますが、それは地球の公転日数の影響によるものだとか…
春分の日といえば「ぼた餅」、秋分の日といえば「おはぎ」ですが、中国では古くから、赤色には邪気をはらう力があるとされており、日本でも赤色には特別な力があると考えられてきました。そのため赤色をした小豆は縁起がよい食べ物とされ、お彼岸にあんこを使ったお餅がお供えされるようになったそうです。ぼた餅は牡丹の花、おはぎは萩の花に由来します。
ちなみに、ぼた餅はこし餡で、おはぎは粒餡で包むという違いがあります。
春分の日に続いて気になるのがお彼岸。これは日本独自の仏教的習慣です。春分の日を中日として前後3日間を含めた計7日間がお彼岸とされています。お彼岸の中日である春分の日と秋分の日はご先祖様を偲ぶ日で、中日以外の6日間は修行をつむ期間。お彼岸におこなわれる修行期間中は、6つの修行を1日ひとつずつおこなうとされています。
さて、今年の春分の日は皆さんどのように過ごされたでしょうか?

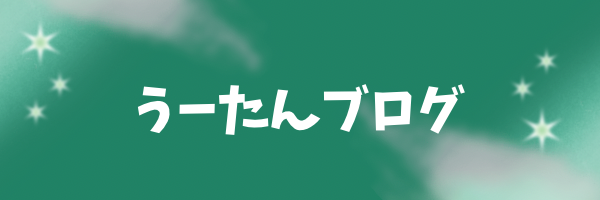

コメント